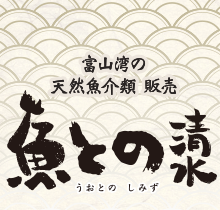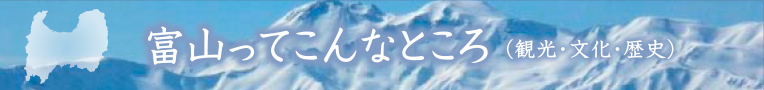取り扱い商品のご紹介


富山県の県鳥であるライチョウ(雷鳥)は、キジ目ライチョウ科の鳥です。
国の特別天然記念物であり長野県、岐阜県の3県の県鳥にもなっています。
ライチョウは、冬でも高山で暮らす唯一の鳥です。
ライチョウが日本にやってきたのはおよそ2万年前の氷河期で、カラフト、カムチャッカを経由し、本州中央部の高山帯に定住しました。氷河期が終わり温暖になったことで大半のライチョウは寒い北へ戻りましたが、ごく一部が日本の高山に残ったと言われています。
現在は北極周辺が主な生息地域であり、日本のライチョウは一番南の端にいるということになります。
現在の日本での生息数は、約3,000羽(北アルプス朝日岳から穂高岳にかけて約2,000羽、南アルプス甲斐駒ケ岳から光岳にかけて約700羽、乗鞍岳に約100羽)とみられています。
天敵のイヌワシなど猛禽類やテンやキツネなどの動物に捕食される以外に、山小屋などから排出されるゴミに混じる病原体や人が持ちこむ感染病によりライチョウが減少することが懸念されています。
また登山者の増加に伴い登山道周辺のハイマツ帯が踏み荒らされ劣勢となり次第に減少しており、それに伴いライチョウの生息数も減少しているほか、温暖化に伴い、ニホンジカやキツネ、ニホンザルの生息域が高山帯に拡大することで餌の競合によっても生息数は減少しています。
ライチョウのその名前は、イヌワシなど猛禽類の天敵を避けるため朝夕のほかに、雷の鳴るような空模様の時に活発に活動することが由来と言われていますが、実際のところははっきりしていません。
夏は褐色、冬は純白と季節によって羽毛の色が変化するのが特徴であり、天敵から身を隠すためと考えられます。
飛ぶことはあまり得意ではないと言われており、基本的にはハイマツ群落内、岩の隙間、雪洞の近くを徘徊しています。
余談ですが、JR西日本が大阪駅―北陸本線(金沢・富山)で運行する特急列車にライチョウと命名し、使用する車両系統により、「雷鳥」「スーパー雷鳥」「サンダ―バード」と区別呼称されていましたが、2011年3月12日のダイヤ改正で全ての列車が「サンダーバード」の呼称に統一されています。
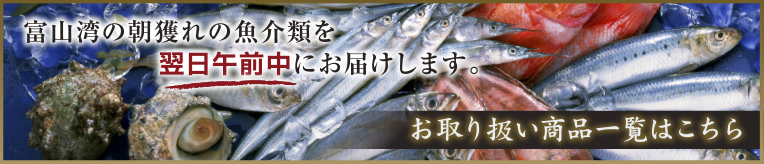
| 富山湾のお魚プロフィール | お魚よもやま話 | 富山ってこんなところ | お買い物ガイド |